


 我々花火愛好家数名は煙火業者が最盛期に向かう2001年6月某日、群馬県は菊屋小幡花火店の工場に招かれていた。
我々花火愛好家数名は煙火業者が最盛期に向かう2001年6月某日、群馬県は菊屋小幡花火店の工場に招かれていた。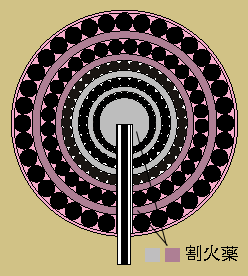 「じゃ、そろそろ始めましょうか」。
「じゃ、そろそろ始めましょうか」。 小幡氏が習得しているのは長野の紅屋青木煙火店の八重芯造りの技法そのものである(写真・現当主、青木昭夫氏の八重芯造り。よどみなく流れるように造りあげていく)。
小幡氏が習得しているのは長野の紅屋青木煙火店の八重芯造りの技法そのものである(写真・現当主、青木昭夫氏の八重芯造り。よどみなく流れるように造りあげていく)。 |
 |
 |
| 星と割火薬を収めるための袋を作業手順に合わせて畳む | 出来上がっている部分までの芯を型となる仮の玉殻に置く | 割火薬と星を交互に足しながら、底の方から順に組み上げる |
 装填した星が天頂に達する頃になると、竹製のピンセットの出番である(写真)。最後のいくつかの星はピンセットで挟んですき間に置いていく。指先との連携で星を微妙に動かしてすき間をこしらえては新たな星を置いていく。全体を回しながら木べらでまんべんなく叩く。そして星と割薬の詰まり具合をならすのである。すると新たな隙間が生じるので、さらに星を足す。これが何度か繰り返されて、ようやく芯部の装填も完了するのである。
装填した星が天頂に達する頃になると、竹製のピンセットの出番である(写真)。最後のいくつかの星はピンセットで挟んですき間に置いていく。指先との連携で星を微妙に動かしてすき間をこしらえては新たな星を置いていく。全体を回しながら木べらでまんべんなく叩く。そして星と割薬の詰まり具合をならすのである。すると新たな隙間が生じるので、さらに星を足す。これが何度か繰り返されて、ようやく芯部の装填も完了するのである。 |
 |
 |
| 割火薬を注ぐ。袋も次第に伸ばしていく | 天頂部まできっちりと星を詰める | 割火薬と星をならすために、全体を叩く |
 小幡氏は闘っている。
小幡氏は闘っている。 夕刻、辺りが薄暗くなり、雷鳴が迫り、やがてバケツを返したような土砂降りとなった。群馬であるなぁ。
夕刻、辺りが薄暗くなり、雷鳴が迫り、やがてバケツを返したような土砂降りとなった。群馬であるなぁ。