|
 平成から令和にかけての30余年、とりわけ2000年代に入ってからの20年、花火業界をそして花火愛好家の私を震撼させ、開拓者以外の花火作家達に多大な影響を与えたであろう画期的な花火作品が多数生み出された。その中でこの30余年を代表する名花は間違いなくこれらであろうと順不同に思いつくままに挙げてみた。
平成から令和にかけての30余年、とりわけ2000年代に入ってからの20年、花火業界をそして花火愛好家の私を震撼させ、開拓者以外の花火作家達に多大な影響を与えたであろう画期的な花火作品が多数生み出された。その中でこの30余年を代表する名花は間違いなくこれらであろうと順不同に思いつくままに挙げてみた。
|
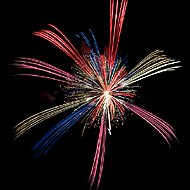 もともとは未来花、ポインセチアと呼ばれていました。それというのも、クリスマスシーズンに花屋の店先を飾るポインセチアをモデルとして、最初は紅と緑が主体の花火だったからです。
もともとは未来花、ポインセチアと呼ばれていました。それというのも、クリスマスシーズンに花屋の店先を飾るポインセチアをモデルとして、最初は紅と緑が主体の花火だったからです。
|
 放射状に丸く開く菊や牡丹とは異なり、夜空を自由気ままに飛び回る星もすっかりポピュラーになっています。これらは総称として「遊泳星(ゆうえいぼし)」「飛遊星(ひゆうせい)」「遊飛星(ゆうひせい)」「飛星(ひせい)」などと呼んでいて業者ごとに呼び名も色々です。ブーンとうなりながらくるくる螺旋を描いて飛び回る「蜂」もその仲間です。星といってもこれらの多くはパイプ星で、ボール紙などで親指くらいの大きさのパイプを造り、その中にさまざまな火薬を詰めます。薬剤と噴出口をあける位置や大きさで、飛び方が色々の星が作り出せます。これらはたいていポカ玉に装填され、打ち上げられます。空中で容器が2つに割れ、点火された中身を夜空にばらまくのです。あとは星自身の推進力で自在に飛び交っていきます。
放射状に丸く開く菊や牡丹とは異なり、夜空を自由気ままに飛び回る星もすっかりポピュラーになっています。これらは総称として「遊泳星(ゆうえいぼし)」「飛遊星(ひゆうせい)」「遊飛星(ゆうひせい)」「飛星(ひせい)」などと呼んでいて業者ごとに呼び名も色々です。ブーンとうなりながらくるくる螺旋を描いて飛び回る「蜂」もその仲間です。星といってもこれらの多くはパイプ星で、ボール紙などで親指くらいの大きさのパイプを造り、その中にさまざまな火薬を詰めます。薬剤と噴出口をあける位置や大きさで、飛び方が色々の星が作り出せます。これらはたいていポカ玉に装填され、打ち上げられます。空中で容器が2つに割れ、点火された中身を夜空にばらまくのです。あとは星自身の推進力で自在に飛び交っていきます。
|
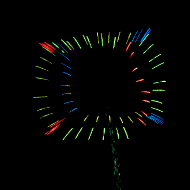 型物花火の基本は平面的(二次元)なものです。正面から見ればある形に見えますが、側面からは線にしか見えません。
型物花火の基本は平面的(二次元)なものです。正面から見ればある形に見えますが、側面からは線にしか見えません。
|
 1998年あたりから全国的に急にポピュラーになってきて2000年度は大流行しています。1990年代始めには、輸入ルートをもつような煙火業者中心に使われ始めています。
1998年あたりから全国的に急にポピュラーになってきて2000年度は大流行しています。1990年代始めには、輸入ルートをもつような煙火業者中心に使われ始めています。
|
 1995あるいは1996あたりから使われ始め、日本の各地の花火大会やイベントでも、最近特に見かける機会が多くなってきました。ゆっくりと上昇する様は、それまでのスピーディな打ち上げとは好対照であるので観客の印象も高く、それぞれがとくに彩りに優れているわけではないにもかかわらず、その運動のユニークなことから好評です。初めて見た観客にはことさら不思議な花火に見えるようです。
1995あるいは1996あたりから使われ始め、日本の各地の花火大会やイベントでも、最近特に見かける機会が多くなってきました。ゆっくりと上昇する様は、それまでのスピーディな打ち上げとは好対照であるので観客の印象も高く、それぞれがとくに彩りに優れているわけではないにもかかわらず、その運動のユニークなことから好評です。初めて見た観客にはことさら不思議な花火に見えるようです。
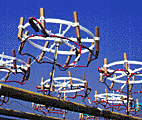 円形の樹脂の(製品の一例、木製や竹製もあります)フレームの周りに、推進用の火薬筒(ドライパーという)が斜めにいくつか取り付けられており、これが上昇と回転運動をもたらしているのです。玩具花火のそれのように、樹脂のフレームはヘリコプターのようなプロペラ状にはなっていません。大きさは色々ありますが流通している商品としては、フレームの直径で25センチから35センチくらいでしょう。点火前は、センターの軸(ボルト)に刺さっていますが、飛んでいくのはフレームの部分だけです。外国ではもっと大型のものも(手作りで)造られ、推進用の花火とは別に星などを搭載して放出する場合もあります。
円形の樹脂の(製品の一例、木製や竹製もあります)フレームの周りに、推進用の火薬筒(ドライパーという)が斜めにいくつか取り付けられており、これが上昇と回転運動をもたらしているのです。玩具花火のそれのように、樹脂のフレームはヘリコプターのようなプロペラ状にはなっていません。大きさは色々ありますが流通している商品としては、フレームの直径で25センチから35センチくらいでしょう。点火前は、センターの軸(ボルト)に刺さっていますが、飛んでいくのはフレームの部分だけです。外国ではもっと大型のものも(手作りで)造られ、推進用の花火とは別に星などを搭載して放出する場合もあります。 ジランドラスは日本の観客に限ったことではなく、欧米の花火ファンにもとりわけ人気の高い花火であるようです。それは美的なものより、それが“自力で飛行する”という点にあると推察します。その例として、花火の最大規模のリンクサイトであるTom Dimock's Pyro Pageでも、わざわざ筆頭にジランドラス専用のページを項目を立てて掲載しています(Girandolasに関する自費出版による冊子も手がけたWebマスターの超お気に入り)。以下の海外のホームページを見ればその愛着ぶりと、手造りによる大型のジランドラスの写真がうかがえるでしょう。
ジランドラスは日本の観客に限ったことではなく、欧米の花火ファンにもとりわけ人気の高い花火であるようです。それは美的なものより、それが“自力で飛行する”という点にあると推察します。その例として、花火の最大規模のリンクサイトであるTom Dimock's Pyro Pageでも、わざわざ筆頭にジランドラス専用のページを項目を立てて掲載しています(Girandolasに関する自費出版による冊子も手がけたWebマスターの超お気に入り)。以下の海外のホームページを見ればその愛着ぶりと、手造りによる大型のジランドラスの写真がうかがえるでしょう。
|
 花火は玉名とおりに開くことを想定して作られています。花火作家が予想するように開かなければ少くとも作り手にとっては意味のないことです。割物芯入りではとりわけその傾向は強く、「八重芯は八重芯に開くから八重芯なのだ」という名人花火師の名言を聞いたことがあります。
花火は玉名とおりに開くことを想定して作られています。花火作家が予想するように開かなければ少くとも作り手にとっては意味のないことです。割物芯入りではとりわけその傾向は強く、「八重芯は八重芯に開くから八重芯なのだ」という名人花火師の名言を聞いたことがあります。
|
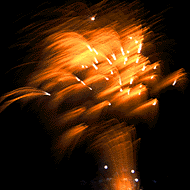 何かが新しいとは、「過去に存在しない」という意味ではありますが、過去に存在していたことを知らない世代にとっては、それは正に新しい未経験の事柄になります。
何かが新しいとは、「過去に存在しない」という意味ではありますが、過去に存在していたことを知らない世代にとっては、それは正に新しい未経験の事柄になります。
|
 花火作家達の長年の工夫によって、現在の花火の星は様々な色彩を創り出すことが可能になりました。1990年代半ばまでは、それらは主に基本原色である、紅、ピンク、黄、橙、緑、青、紫、金、銀(白)、錦などでした。この中でもピンクや紫は比較的新しい色であるといえます。もちろん色合いはそれを作る煙火業者によって微妙に異なります。
花火作家達の長年の工夫によって、現在の花火の星は様々な色彩を創り出すことが可能になりました。1990年代半ばまでは、それらは主に基本原色である、紅、ピンク、黄、橙、緑、青、紫、金、銀(白)、錦などでした。この中でもピンクや紫は比較的新しい色であるといえます。もちろん色合いはそれを作る煙火業者によって微妙に異なります。
|
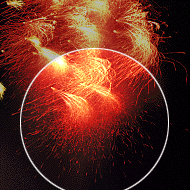 1997年あたりの新作競技会などで、初めて目にしました。写真などで表現するのは難しいのですが、主にポカ物に仕込む星で、上空で空中に放出された後は、ひとかたまりになってそれぞれの星が大きく震えるように動く、という変わった物です。もとはズバリ輸入ものでしょう。単体の星は夜空ではとても小さな物で、光も弱めなのでボリューム感に欠けるといえるでしょう。動きは可愛らしいのですが、蜂のように大きく動き回るわけではないので、ある程度物量を打たないと効果的ではありません。色は紅、緑、銀などです。
1997年あたりの新作競技会などで、初めて目にしました。写真などで表現するのは難しいのですが、主にポカ物に仕込む星で、上空で空中に放出された後は、ひとかたまりになってそれぞれの星が大きく震えるように動く、という変わった物です。もとはズバリ輸入ものでしょう。単体の星は夜空ではとても小さな物で、光も弱めなのでボリューム感に欠けるといえるでしょう。動きは可愛らしいのですが、蜂のように大きく動き回るわけではないので、ある程度物量を打たないと効果的ではありません。色は紅、緑、銀などです。
|
|